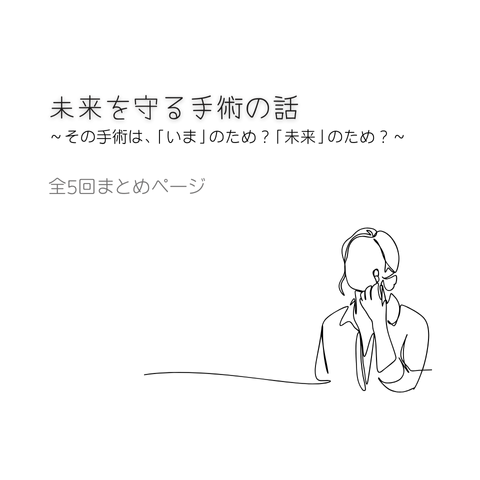
【総集編】未来を守る手術の話 全5回まとめ...
2025/08/21

2025/04/03
産婦人科医の錢瓊毓(せん けいいく)です。「ミレーナ」って聞いたことありますか?聞いたことあるけれどよく知らないなぁ、という方のために、ミレーナについて解説します。
避妊方法について検討中の方や過多月経(生理の量が多い)で悩んでいる方は、ぜひ読んでください!
ミレーナとは、バイエル社が提供する「子宮内黄体ホルモン放出システム(IUS: Intrauterine System)」1の製品名です。海外では複数のIUS製品が存在しますが、日本ではミレーナのみが販売されています。そのため、IUSよりはミレーナという名称の方が有名になっています。本記事ではIUSのひとつである「ミレーナ」という製品について説明をします。
ミレーナは、子宮内に装着する小さなT字型の器具で、黄体ホルモン(レボノルゲストレル)を持続的に放出します。その働きにより、以下の効果が得られます。
低用量ピルは卵巣を休めさせることで排卵を止めますが、ミレーナの場合は子宮内膜に働きかけるだけで、卵巣に対する影響はありません。低用量ピルとミレーナの大きな仕組みの違いはこの点にあります。
ミレーナは、単なる避妊手段ではなく、過多月経や月経困難症の治療にも使用されます。避妊にしても過多月経の治療にしても、ミレーナか低用量ピルか、という選択肢で検討していくことが多いです。どちらを選択しても、以下のような効果が期待できます。
妊娠をトライする段階になったら、ミレーナを除去すれば速やかに妊娠可能な状態に戻ります。ミレーナ使用中も排卵は止まっていないので、早ければ1か月ぐらいで妊娠することもあり得ます。
日本では、ミレーナの有効期間は最長5年間と承認されています。一方、海外では8年間の避妊効果が報告されており、製造元のバイエル社も海外向け情報では8年間の有効性を発表しています(2025/4時点)。ミレーナという名前は同じでも日本と海外では売っている製品が違うのでは?と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。私もそこが気になったので、日本のバイエル社に問い合わせたことがあります!返答は「日本も海外も同一製品です」とのことでした。
同じミレーナなのに、日本の風土のせいで有効期間が減っちゃうの?なんてことはあるはずがありません。日本において有効期間5年で申請し承認されている、というだけです。ミレーナの避妊効果が8年というデータは新しく蓄積されたものなので、日本で再度承認申請をしないと公式に8年有効と謳うことはできません。しかし、この承認申請のプロセスはお金と労力を要します。メーカーとしては、ここに力を注ぐメリットがない、という大人の事情なのだと私は推察しました。(あくまでも私個人の推察です!)
ただし、黄体ホルモンの放出量は年数とともに減少するため、過多月経治療として使用する場合は5年ごとの交換が推奨されます。避妊目的であれば、個々の状況に応じて8年まで延長できると理解してください。
ミレーナの利点は「一度装着すれば長期間効果が持続する」ことですが、その反面、装着と除去は必ず医師が行う必要があります。この点が低用量ピルとは大きく異なります。低用量ピルは、効果を持続させるためには毎日服用しなければいけませんが、飲み始めるのも止めるのも、ご本人がコントロールできます。
ミレーナ装着時期や方法について医師と十分に相談し、最適なタイミングを決めてください。装着後は、適切な管理のために定期的な診察を受けることが重要です。
「ミレーナは出産経験のある人向け」と誤解されることがありますが、未産婦でも使用可能です。未産婦の場合、子宮の入口が狭いため、挿入時に痛みを感じることがあるとされていますが、私の臨床経験では特別に強い痛みを訴えるケースは多くありません。挿入前に医師と十分に相談し、必要に応じて痛み止めを使用することで、不安を軽減しながら処置を受けることができます。
ミレーナはどんな方でも使用可能ですが、特に以下のような方にお勧めです:
◆ 20代前半で当面妊娠予定のない方
◆ 出産を終えて今後妊娠予定のない方
◆ 低用量ピルを飲み忘れがちでうまくいかない方
避妊目的だけでなく、過多月経の治療にも有効なミレーナは、出産経験の有無を問わず、多くの女性にとって有力な選択肢となります。ご自身にとってミレーナがいいのか、または低用量ピルがいいのか、は、それぞれのライフスタイルや今後のライフプランによるところが大きいです。まずは産婦人科で相談し、ご自身にとっての最適な方法を見つけてください。
芦屋ウィメンズクリニックでは、ミレーナ装着希望の方には随時対応しています。過多月経の治療目的の場合は保険適応、避妊目的の場合は自費診療(保険適応なし)となります。興味はあるけど決めかねている、という方は、お話だけでもかまわないので、一度受診してください。ご自身にとってメリットとデメリットのどちらが大きいのかを一緒に考えていきましょう。
芦屋ウィメンズクリニックについて
🚉 JR芦屋駅から徒歩3分
🏥 芦屋市大原町5-19 芦屋大原町医療ビル 4階 Google Map
🕒 月火木金:10:00〜13:00 / 15:00〜19:00
土:10:00〜17:00(13:00以降は完全予約制)
水日祝:休診
🏠芦屋ウィメンズクリニック公式サイト