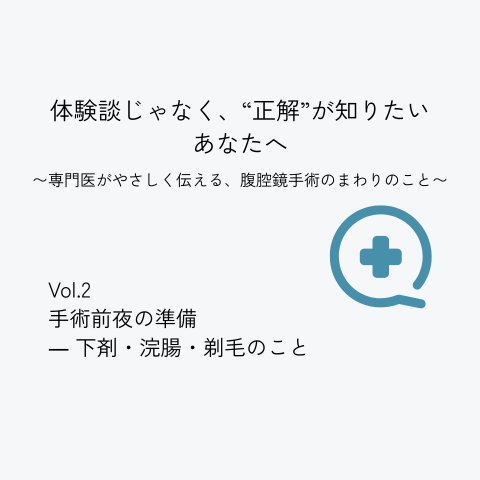
体験談じゃなく、”正解”を知りたいあなたへ_第2回...
2026/01/31

2025/01/23
医師の錢瓊毓(せんけいいく)です。月経前症候群(PMS)は、産婦人科医が担当する疾患ですが、場合によっては精神科・心療内科医の協力を得ることもあります。私自身は、東京・神田にある心療内科のベスリクリニックで診療に携わる機会に恵まれ、PMSで悩んでいる女性がいかに多いかを知りました。産婦人科領域にいるだけでは見えなかった現状を知り、自分自身の知識とスキルをさらに磨かねばと反省しました。今日は、その経験を反映させたいと思い、PMSについて書くことにしました!
月経前症候群、略してPMS(Premenstrual Syndrome)は、月経(生理)が始まる前の数日から2週間程度の間に現れる、さまざまな身体的・精神的な症状の総称です。多くの女性が経験するこの症候群は、女性ホルモンの変化が主な原因となっています。
具体的には、エストロゲンとプロゲステロンという2つの女性ホルモンのバランスが大きく変動することで、体と心に多様な影響を与えます。実際、女性の約75%が月経前に何らかの症状を経験すると言われており、決して特別なことではありません。
PMSの症状は多岐にわたり、身体的なものと精神的なものがあります。身体的な症状には、腹痛、むくみ、乳房の張り、頭痛などが含まれます。一方で、精神的な症状としては、イライラや気分の変動、疲れやすさ、集中力の低下が挙げられます。
これらの症状の多くは、生理的現象といえる程度にとどまることが多く、不快だけれど我慢できるものです。ただ、中には学業や仕事でのパフォーマンスが低下したり、友人や家族との関係にトラブルが生じたりすることも珍しくなく、日常生活に大きな影響を与えることがあります。医学的には、上記のような症状により日常生活に支障をきたし、治療を求めるような状態をPMS(月経前症候群)と呼びます。
PMSの症状は多彩です。その理由は、PMSの原因だといわれている性ホルモンがほぼ全身の臓器に作用するからです。性ホルモンとPMSの関係については、次の段落で説明します。
PMSの発症は、主に性ホルモンの変動に関連しています。生理周期の前半は、卵巣からエストロゲンというホルモンが分泌されます。そして、排卵後は卵巣からプロゲステロンというホルモンが分泌されます。そして、プロゲステロンに曝露されることで、PMS症状が出現します。
専門的過ぎる話は割愛して結論だけをお話すると、プロゲステロンには以下のような作用があります:
プロゲステロンがもつこれらの特性によって、PMS症状が出やすい状態が作られるのです。
日常生活の負荷と、個々の女性の固有の性格・経験・適性、周囲の理解・メンタル面の強靭性などの相互関係でPMSの発症は規定されます。つまり、外的因子と内的因子とが相互に影響を及ぼしあうと考えられています。外的因子とは、仕事や学業、人間関係など、その人を取り巻く何かだと考えてください。
「年々PMS症状が悪化している」とおっしゃる方がしばしばいらっしゃいます。年齢を重ねる中で、自分を取り巻く環境はより複雑化し、かつ、担う責任は大きくなります。負荷が増えているので、PMS症状が悪化するのはある意味当然です。例えば、「出産後にPMSが悪化しました」と伺うことがよくあります。出産したことでPMSが悪化しているのではなく、子供という「とても大切な存在だけれど思い通りにできない別人格」が人生に現れたことで、ご自身の責任が重たくなっただけでなく、家庭内の役割や生活が大きく変わっているので、負荷が増えたことによるPMS悪化なのだと私たちは捉えています。
PMSを自己診断するには、まず自分の症状を記録することが有効です。症状の出る時期やその程度を把握することで、どの程度の問題かを理解しやすくなります。
以下のような症状について、セルフチェックしてみてください。
PMS診断の決め手となるのは、症状の種類よりもむしろ「症状の発現時期」です。症状がみられるのは、「排卵が過ぎて生理が始まるまでの時期」に限られています。生理周期には個人差がありますが、どの人にも共通しているのは「排卵は生理開始の14日前に起こる」ということです。排卵した後にプロゲステロン(黄体ホルモン)が卵巣から分泌され、排卵から生理が始まる前までの間を「黄体期」と呼ぶのですが、この時期のみ、PMS症状が出現します。前述どおり、PMSはプロゲステロンに曝露されないと発症しないので、言い換えると、排卵をしていない人(無月経、妊娠中、閉経後など)は厳密な意味でのPMSはありません。
典型的なPMSの方は、「いつもならなんともないことなのに、生理前だと涙が出る/くよくよする/自分はなんて価値のない人間なんだろうと思う。ところが、生理が始まったら、なんであんなふうに感じたのかな?と思う」という感じです。
PMSの治療には、まずライフスタイルの改善が重要です。栄養バランスの取れた食事や定期的な運動、規則的な睡眠は、心身の健康を保つために欠かせません。アルコール類やカフェインは控えめにし、喫煙は止めましょう。
食事は、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、ビタミンD、ビタミンB6、ビタミンEを含むものを意識してほしいのですが、実際、これらのミネラルやビタミンを補充さえすれば確実に効果が期待できるというわけではありません。多忙、ストレス、食事の偏りなどが複合的にPMSにかかわっていると推察できるので、「落ち着いてバランスの良い食事を摂ることができる環境」に身を置くことが最終目標だと思って、少しでもここに近づくことをイメージしてやってみてください。
適度な運動はエンドルフィンを分泌させ、気分を明るくする効果があるだけでなく、黄体期のプロゲステロンの分泌を低下させます。なお、症状がない時期も含め、継続することが大切です。
具体的な改善例として、日常的に運動を取り入れたり、ストレス管理のための趣味を持ったりすることで、多くの女性が症状を軽減しています。
薬物療法を行うかどうかの判断は、症状がどの程度日常生活に影響を与えているのか、薬の効果と副作用などをよく理解した上で、ご本人が選択するものです。また、薬物療法が有効であっても、複数症状のうち改善する症状と変化がみられない症状もあります。すべての症状が改善することが理想ではありますが、一番困っている症状を標的にして治療を行うのが良いでしょう。
低用量ピル、少量の抗うつ薬、漢方を単剤または組み合わせて治療を行います。医師とよく相談して、どの薬を使うのかを決めてください。
PMSは多くの女性が経験するもので、決して一人だけの問題ではありません。症状を理解し、適切な対策を講じることで、より快適に過ごすことができるようになります。
自分だけがこのような状態にあるのではないかと不安を感じる方もいるでしょう。PMSに悩んでいる場合は、ぜひ受診を検討してください。医師とのコミュニケーションを通じて、自分に合った治療法を見つけることができます。
PMS症状に悩んでいる方は、ぜひご相談ください。来院が難しい場合は、オンライン診療もご利用いただけます。あなたの健康をサポートさせてください!